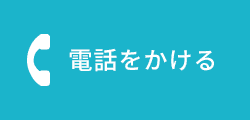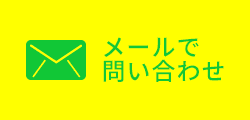親知らず治療
親知らずとは、一番奥の歯(12歳臼歯)のさらに奥に生えてくる歯のことです。
正式には「第三大臼歯」と言い、永久歯の中で最も遅く20歳前後に生えてくることが多いため、「親が知らないうちに生える歯」としてこの名で呼ばれています。
すべての親知らずを抜く必要はありません
「親知らずは、必ず抜かなければいけない」と思われている方も多いかもしれません。
しかし他の歯と同じようにまっすぐキレイに生えてきて、歯みがきもしっかりとできている場合には必ずしも抜歯を行う必要はありません。

抜歯を検討した方が良いケース
一方で下記のように、将来的にむし歯や歯周病、歯並びの悪化といった様々なトラブルを引き起こす可能性が高い親知らずは、痛みなどの症状が出る前に早めに抜歯しておくことがお口全体の健康を守る上で賢明な選択となる場合があります。
親知らずが原因となる主なトラブル
・横や斜め、あるいは骨の中に埋まったまま生えてこない
・歯ぐきが被っており、汚れが溜まりやすく、腫れや痛みを繰り返している
・一番奥にあって、歯ブラシが届かずむし歯になっている
・隣の健康な歯を押して、歯並び全体を乱す原因となっている
当院の安全で痛みに配慮した抜歯の流れ
- STEP1:精密な検査と丁寧なご説明
- 安全な抜歯は、まず、現在の状態を正確に把握することから始まります。
レントゲン撮影を行い、親知らずの生え方や、根の状態、そして、すぐ近くにある太い神経や血管の位置を、三次元的に詳しく確認します。
この徹底した事前準備が、安全な抜歯の土台となります。検査結果をもとに、抜歯の必要性や手順、起こりうるリスクについて、患者様がご納得いただけるまで、丁寧に説明いたします。
- STEP2:痛みを最小限に抑える麻酔
- 当院では、治療中の痛みを極力感じさせないよう、麻酔の方法にも、きめ細かな配慮をしています。
表面麻酔
いきなり注射針を刺すことはありません。まず、麻酔を打つ部分の歯ぐきに、ゼリー状の「表面麻酔」を塗布し、粘膜の感覚を麻痺させます。
電動麻酔器の使用
表面麻酔が効いてきたら、注射麻酔を行いますが、その際にも「電動麻酔器」を使用します。
コンピューター制御によって、非常にゆっくりと、一定の圧力で麻酔液を注入できるため、注射の際に生じる、特有の痛みや不快感を、最小限に抑えることができます。
- STEP3:抜歯の実施
- 麻酔が十分に効いていることを確認してから抜歯を開始します。
抜歯中は歯を押したり動かしたりする感覚はありますが、麻酔が効いているため、鋭い痛みを感じることは基本的にありません。
まっすぐに生えている場合
歯と骨の間にある「歯根膜」というクッションのような組織に専用の器具を差し込み、歯を骨から、てこの原理で優しく引き離すようにして抜いていきます。
横向きや、骨に埋まっている場合
骨の奥深くにもぐっている親知らずの場合は、歯ぐきを少し切開し、歯の頭を見える状態にします。
そして、歯をそのまま抜こうとすると、周りの骨に大きな負担がかかるため、歯をいくつかに小さく分割してから、丁寧に取り除いていきます。 頑張ってお口を少し長めに開けていただく必要がありますが、安全で、体への負担も少ない方法です。
- STEP4:縫合と止血
- 抜歯した後の穴は、血液が溜まって「血餅」というかさぶたができることで、治癒していきます。
この血餅がうまくできるように傷口を糸で縫い合わせて小さくしたり、止血用のスポンジを入れたりする場合があります。
- STEP5:抜歯後の消毒と経過の確認
- 通常、抜歯の翌日に一度ご来院いただきます。
出血や感染がないかを確認し、傷口を消毒します。 痛みや腫れの状態に応じてお薬の種類を変えるなど、より早く楽に回復するよう調整します。
- STEP6:抜糸と治癒の完了へ
- 抜歯からおよそ1週間が経過すると、歯ぐきの傷口がある程度ふさがってきます。
このタイミングで、縫い合わせた糸を取り除きます(抜糸)。 その後、3~4週間ほどで、歯ぐきの穴は完全にふさがり、その下の骨は、3~6ヵ月程度かけて、ゆっくりと回復していきます。
万が一のトラブル「ドライソケット」について
通常、抜歯後2~3日で落ち着くはずの痛みが、1週間経っても、むしろ強くなるような場合があります。
その場合、「ドライソケット」になっている可能性があります。
これは、抜歯した穴のかさぶた(血餅)が、強いうがいなどによって剥がれてしまい、骨が直接お口の中に露出してしまっている状態です。痛みを伴います。
強い痛みが続く場合は、決して我慢せず、すぐにご連絡ください。
ドライソケットになっている場合は、傷口をきれいに洗浄し、抗生物質などのお薬を入れることで、痛みを和らげ、新たな血餅ができるのを待ちます。
適切な処置を行えば、必ず治りますのでご安心ください。